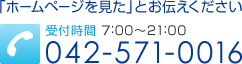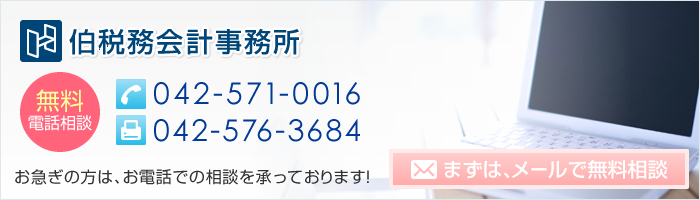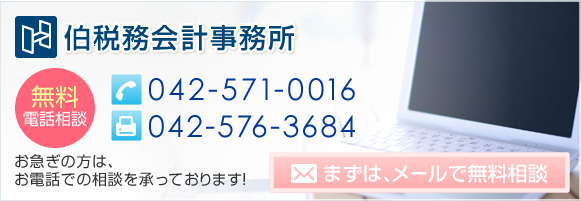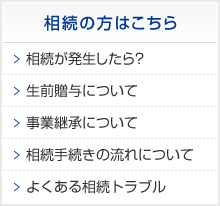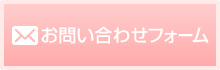【一獲千金の税務処理はお忘れなく】
2025.12.01更新
一獲千金には夢がありますが、その後の税務処理を怠ると大きなリスクとなります。
競馬や競輪などの公営競技の払戻金は、原則として一時所得に分類されます。
例えば趣味で馬券を購入する一般の愛好家の場合、外れ馬券代は必要経費としては認められず、当たり馬券代だけが控除の対象となります。
年間50万円までの払戻金は申告する必要はありませんが、払戻金から当たり馬券代を差し引いた残額が50万円を超えると、その超過分の半額が課税対象となります。
一方、自動購入ソフトなどを用いて網羅的に購入し、継続的かつ営利目的で取り引きしていた場合は雑所得に該当します。
このような場合には、外れ馬券代も経費算入が認められると裁判所が判断しました。
また国税庁は、ネット購入履歴の蓄積データを通じて課税の適正化を進めており、国の行政機関である会計検査院も高額払戻しの未申告を課題と指摘しています。
宝くじが非課税であるのと対照的に、公営ギャンブルでは夢と税負担が表裏一体にありますね。
投稿者: