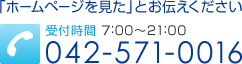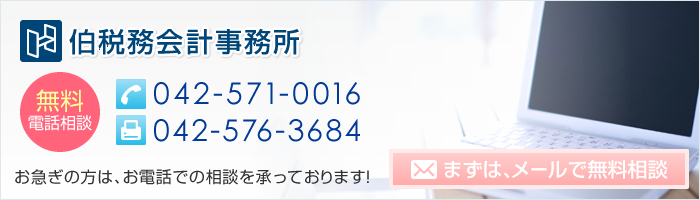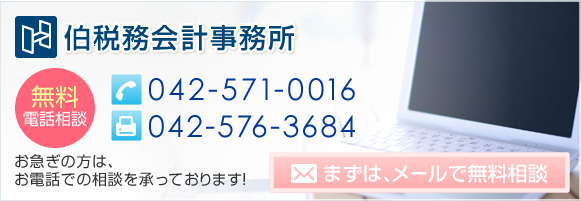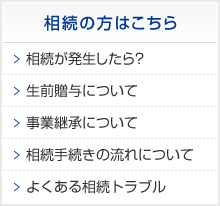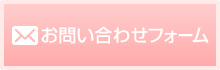【植物に学ぶ人生の知恵】
2025.03.15更新
植物の生育過程には、私たちの人生に通じる深い知恵が隠されています。
例えば麦は若芽の時期に踏まれることで、かえって力強く成長します。
乾燥地帯の木々は、水を求めて太い根を地中深くまで伸ばし、その結果として強風にも耐えうる強靭(きょうじん)さを獲得します。
またトマトは必要最小限の水で育てたほうが、より凝縮された味わい深い実をつけることがよく知られています。
これらの自然の摂理は、私たちの人生における困難や試練の意味を考えさせてくれます。
快適な環境で育った植物は、表面的には順調に見えても、実は浅い根しか持たず、わずかな風雨で倒れてしまいかねません。
同様に人生における日々の苦労や困難は、私たちの内面に深い根を張らせる機会となります。
苦境に直面したとき、それを単なるつらさとして避けるのか。
それとも自己を強化する機会と捉え直すのか。
それは新たな商売への挑戦かもしれませんし、人間関係のいざこざ、あるいは健康上の問題かもしれません。
いずれにしても困難だと感じるのは、まだその経験が不足しているからともいえるでしょう。
誰もが何らかの苦労を抱えています。表面的には順風満帆に見える人の人生も、実は見えないところで深い根を張る努力を重ねているかもしれません。
逆境こそが私たちを成長させる肥沃(ひよく)な土壌となり、つらい状況は自己を強化できるありがたい出来事となる。
そう解釈できたら、日々の困難は、より大きな試練に備えるための準備期間となるに違いありません。
何事も忍耐強く取り組めば、やがてその苦労は糧となり、想像以上の強さを身につけることができると信じて進みたいものです。
投稿者: