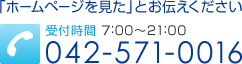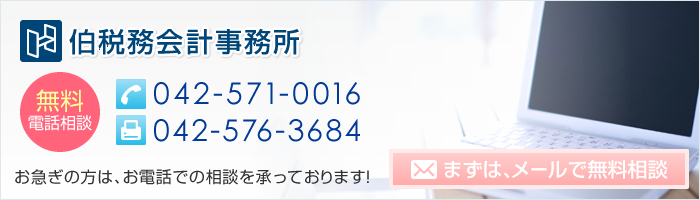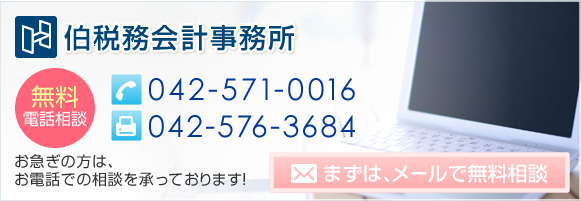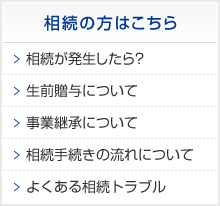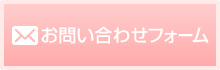【青き踏む春に遊ぶ】
2019.05.15更新
ぬくぬくとした日だまり。心がとろけそうになるやわらかな風。
あたりの緑は色濃くなり、いっせいに花が咲き始める。
春は、四季のある国に暮らす喜びを全身で感じられる季節です。
陰陽五行で春の色といえば「青」。
これが「青春」の語源だとされています。
俳句の世界では、春先の野原で青草を踏んで遊ぶことを「青き踏む」、または「踏青(とうせい)」といいます。
もとは古代中国の行事に由来する言葉で、旧暦3月に青草がもえる中でうたげをする春の恒例行事だったそうです。
ところで、春から夏に向かう頃になるとイソップ童話の『北風と太陽』を思い出すという知人がいます。
旅人の外套(がいとう)を脱がせるために北風と太陽が勝負をするお話です。
北風は思い切り寒い風を吹かせて旅人の外套を吹き飛ばそうとしますが、風が吹けば吹くほど旅人は外套の前をしっかり押さえます。
一方の太陽は、暖かな日差しを旅人に浴びせ続けました。
するとそのうち旅人は暑くなり、自ら外套を脱ぎました。
勝負は太陽の勝ちです。
乱暴なやり方ではうまくいかない。
優しい言葉をかけたり温かい態度を示したりすると、人は自分から行動する。
一般的な教訓では、こうして北風が悪者になっています。
ところが、実は2回勝負したという説もあるようです。
まずは旅人の帽子を脱がせる勝負をしました。
太陽が燦々(さんさん)と旅人を照らすと、あまりのまぶしさに旅人は帽子をしっかりかぶってしまいます。
次に北風が力一杯に風を起こすと、旅人の帽子はいとも簡単に吹き飛んでいきました。
勝負は北風の勝ちです。
そこでもうひと勝負というわけで、外套を脱がせる2回戦が始まったのだとか。
このストーリー教訓は「何事にも適切なやり方というものがあり、一方でうまくいっても他方でうまくいくとは限らない」というものです。
押してもダメなら引いてみる。
商売の信念がコロコロ変わってはなりませんが、商売のやり方や考え方はひとつではないでしょう。
煮詰まったときは昔の人にならって「青き踏む」を楽しみ、一度しか巡って来ないこの春を喜びと共に過ごしたいものですね。
投稿者: