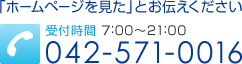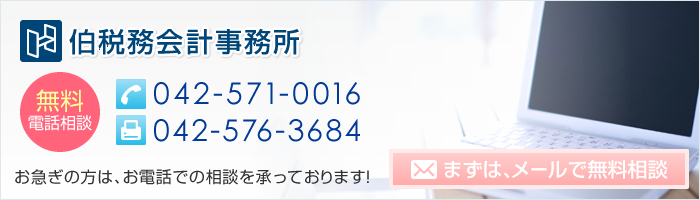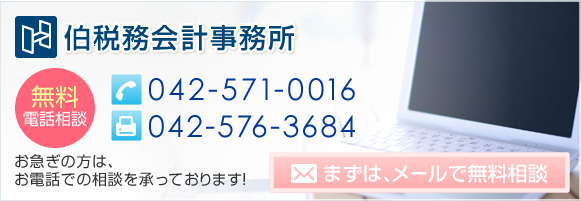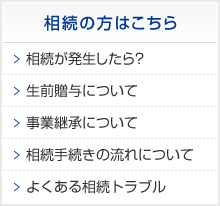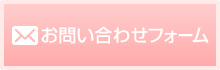2008.11.15更新
・【宝くじで3億円を手に!では、支払う税金はいくら?】
・年末ジャンボ宝くじの発売時期になると、長い行列をつくっている宝くじ売場を見かけることもしばしばあります。
・列を作っている人たちは「もし、宝くじで3億円を手にしたら...、マイホーム、新車、海外旅行に高級ブランドのバック、靴に洋服...」そんな楽しい夢を描きながら並んでいることでしょう。
・さて、そんな夢を描いて購入した宝くじが運良く当選して3億円を手にした場合、そのお金にはどれだけの税金がかかるのでしょうか?
・答えは「0円」。
・つまり、宝くじの当選金には税金はかかりません。しかし、当選したお金を家族にお小遣いとしてあげると、その額によっては贈与税が発生します。
・では、「お金」がダメなら「物」で、ということで子供に「子供名義」の車を買ってあげたとしても贈与税はかかります。
・「じゃあ、生前贈与はどうなの?」というお声も聞こえてきそうですが、生前贈与(相続時精算課税制度)を利用した場合は、相続が発生したときに生前贈与をした分を相続財産に加えて計算をしなければなりません。
・また、その他の諸条件もありますから、資産状況や今後の計画など、多くの観点から慎重に検討しなくてはいけません。
・宝くじは、当選するのも難しいですが、その後の対策もなかなか厄介なものです。
・3億円が当たった場合には、一人では悩まずにコッソリご相談くださいね。
投稿者: 伯税務会計事務所
2008.10.16更新
独身税!?
・少子高齢化がますます進んでいく日本です。
・その状態が続くと現役世代が減って高齢者が増えるため、現役世代の負担がだんだん重くなっていきます。今現在3人で1人の高齢者を支えている状態が、2025年には「2人で1人を支えなくてはいけない」という予測もあります。
・そんな少子高齢化の現状を打開するため、以前にある国会議員が「独身税の導入」を提案したことがあります。この「独身税」ですが、その昔ブルガリアで少子化対策として実際に導入されたことがある税金なのです。ブルガリアは、人口800万人ちょっとの国で、少子高齢化による労働人口不足という大きな問題を抱えていました。
・そこで考えられた税制が、独身の人に対する「独身税」というものだったのです。この「独身税」は、1968年から1989年の21年間にわたって導入され、収入の5~10%の税金を徴収するというものでした。ブルガリアでは「独身税」導入後、思惑通り既婚率が増加し出生率も増加・・・となればよかったのですが、残念ながら出生率は、2.18から1.86となってしまったようです。
・「独身税」をもってしても、出生率の減少を食い止めることは、なかなか困難だったようです。なんでも増税といったペナルティ式の方法ではなく、違った形での問題解決が必要なのかもしれませんね。
投稿者: 伯税務会計事務所
2008.09.20更新
【社員教育をすると節税になる制度とは?】
・「人材投資促進税制」が平成20年度に改正されました。この「人材投資促進税制」とは、人材育成に積極的に取り組む企業に対し、教育訓練費の一定割合を法人税から控除するという制度です。
・これは平成17年度にできた制度ですが、改正前は適用年度の教育訓練費が前期2期分の平均に対して増加することが必要でした。
・ところが、今回の改正により、教育訓練費の増減にかかわらず適用できるという利用しやすい制度に変わりました。
・中小企業(原則、資本金1億円以下の青色申告法人)においては、適用年度の労働費用(従業員の給与など)に対する教育訓練費の割合が0.15%以上という条件です。気になる控除額は、教育訓練費の8~12%です。
・例えば、適用年度の労働費用が2000万円で、教育訓練費に50万円を使った場合は、労働費用に対する教育訓練費の割合が2.5%となるので適用対象となります。この場合ですと教育訓練費50万円の12%が控除できますので、6万円を納める税金から控除することが可能です。
・また、大企業については適用期限平成17年4月1日~平成20年3月31日までに開始する事業年度で廃止となります。
・なお、この制度について、詳しいことをお訊ねになりたい場合は、お気軽にご相談ください。
投稿者: 伯税務会計事務所
2008.08.18更新
棚卸商品の評価方法で節税
・「売れ残った商品」というのは、困りものですね。特に決算のときには「売れ残った商品」は、棚卸で資産に計上しなくてはいけません。
・税法では、棚卸商品の評価は原則「仕入れたときの値段」つまり取得価額で評価されます。
・しかし、例外的に評価損を計上できる場合があります。それは「著しい陳腐化」や「型くずれ」「品質変化」などがあったときです。
・例えば、1000円で仕入れたものが、期末時点では500円くらいの価値しかなければ、差額は「評価損」として利益を圧縮することができます。しかし、 ここで問題となるのが「本当に500円の価値しかないのか?」ということです。税務署に対して客観的な証拠がないと、その評価損が認められない場合があり ます。
・そこで、そのようなときの1つの手段として、決算大バーゲンという方法があります。決算前に実際に処分バーゲンをおこなえば、「処分バーゲン」をしても 売れ残ってしまった「それだけの価値しかない商品」という客観的な証拠を残すことができます。そのまま棚卸商品として持っていたとしても利益を生むどころ か、逆に倉庫代などの維持管理費がかかってしまうような場合には、少々赤字でも節税も兼ねて、決算前のバーゲンで見切りをつけるという選択も1つの方法で す。
・本当は、最初から売れ残らずに、全部売れてくれるのが1番ですけどね・・・。
投稿者: 伯税務会計事務所
2008.07.26更新
ふるさと納税
・今年の5月から「ふるさと納税」制度がはじまりました。
・この制度は、大都市と地方との税収の格差を是正する手段の1つとして、新しく導入されました。その仕組みは、個人が今住んでいる場所(住民票のある居住 地)以外の自治体に寄付をした場合、寄付金相当額が、今住んでいる自治体の住民税などから控除されるようになっています。
・寄付の対象となる自治体は、「生まれ育ったところ」から「一度も住んだことのないところ」まで、すべての都道府県、市区町村から自由に選ぶことができます。
・なお、控除の対象となる寄付金は5000円以上となります。たとえば、6000円を寄付すると1000円相当の控除を受けられます。また、控除できる金額には上限があり、住民税の所得割の1割(住民税のほぼ1割)となっています。
・この「ふるさと納税」制度は、寄付の文化があまり根付いていない日本では「さほど普及しないのでは!?」という声もある一方で、出身地だけでなく好きな 自治体に寄付できることから、全国の自治体が寄付集めに知恵をしぼり、いろいろな方法で「ふるさとの魅力アピール」に乗り出すと、利用者は急増するとの見 方もあるようです。
投稿者: 伯税務会計事務所
2008.06.01更新
消費税のあれこれ
・日本で消費税が導入されたのは平成元年4月1日でした。その消費税も、今年で20年を迎えました。すっかり定着した消費税ですが、導入時は3%だったことは、まだご記憶にあるかとは思います。
・税率が5%にアップしたのは、平成9年4月1日です。5%になってからは、もう11年が経過しました。消費税導入後10年弱で5%にアップし、それから 11年が経過した近頃では、更なる税率アップの雰囲気が漂う日本ですが、世界の国々では、消費税というものは存在するのでしょうか?
・実は消費税は、世界136カ国で導入されています。お隣の韓国の消費税率は10%、今年のオリンピック開催地の中国は17%になります。では、消費税率が世界で1番高い国はどこでしょうか?
・それは「スウェーデン」「デンマーク」「ノルウェー」で、その税率は何と「25%」です。では世界で1番低い税率は?と言いますと「シンガポール」「台湾」そして「日本」などの「5%」になります。
・こうして見ると日本の消費税率は、導入国の中では1番低いことがわかります。しかしヨーロッパなどでは「生活必需品」においては「消費税率0%」という 国もありますし、何と言っても税金は、どのように活用されるかが重要になります。そのため、一概に税率が低いから「安い」と言えないのが難しいところです ね。
(2006年9月時点のデータを参照)
投稿者: 伯税務会計事務所