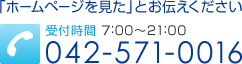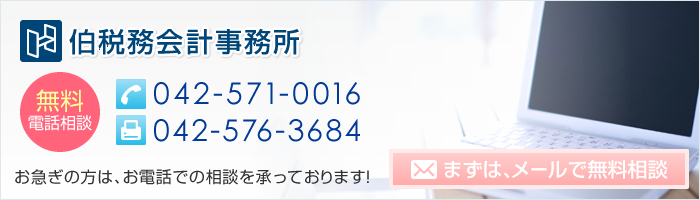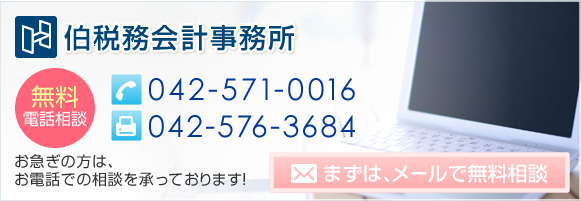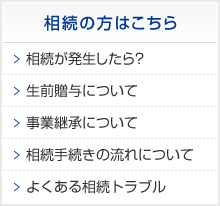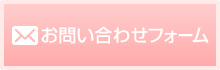【アホウドリに学ぶ商売の知恵】
2016.10.15更新
「アホウドリ」という名前の鳥がいます。
一説には、ほとんど人間と接触しないので警戒心が少なく、簡単に捕まえられるアホな鳥だからという不名誉な理由でその名が付いたそうです。
ところが、アホウドリはとても賢い人生設計で生きています。
野生のアホウドリの寿命は15年から20年。野鳥では異例の長生きです。
1年に1回だけ産卵し、1回の産卵では1個の卵しか産みません。
産卵後はほぼ1年かけてひなをかえし、育てて教育します。
ひなの育成には多くの時間がかかるので卵を産まない年もあります。
子育てする場所は絶海の孤島。
場所は限られている反面、哺乳類などの外敵が来ないので安全に子育てできます。
外敵の少ない孤島で長生きして子どもを大切に育てる。これがアホウドリの人生設計です。
己をよく知った上での見事なやり方ですね。
アメリカのミッドウェー環礁国立自然保護区には、特に賢いアホウドリが住んでいます。推定年齢65歳以上。
確認されている限りでは世界最高齢の野鳥というだけでも大したものなのに、つい数年前にも産卵し、これまでに30羽以上のひなを育てあげたそうです。
環境汚染などで生存環境が悪化する中、通常の3倍以上も生き続ける大ベテランのこのアホウドリを研究者たちは「ウィズダム(知恵)」と呼んでいるとか。
肩書きが社長でも経営者にはなれません。
経営者と呼ばれることはあっても、実際に経営ができなければニックネームと同じになってしまいます。
「経営者の仕事はシミュレーションに尽きる」と言った人がいますが、確かに経営には知恵が必要です。
ひょうひょうとしながらも商売がうまくいっているなら、その人は陰で何十回もシミュレーションをしてお金と人を動かしているのかもしれません。
自分をよく知り、優先順位を的確に判断してシミュレーションを繰り返し、最善の策を取っていくのが経営だとすれば、アホウドリは立派な経営者です。
経営者というニックネームに甘んじてはいけません。
アホウドリに負けない商売設計で先へ先へと進んでいきたいものですね。
投稿者: