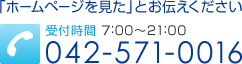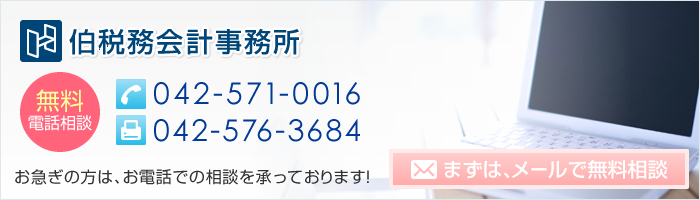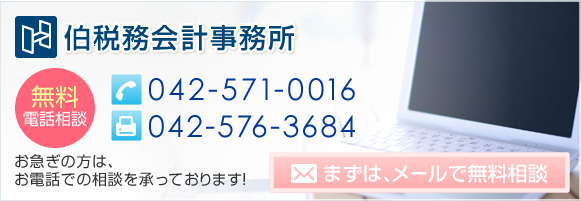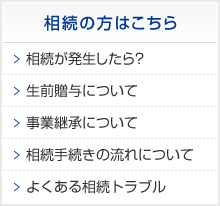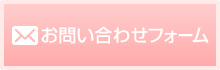【「今年こそ!」から「今日こそ!」へ】
2016.01.15更新
お正月の風景もずいぶん様変わりしました。
例えば福袋。
かつては「お楽しみ」だった中身があらかじめ公開され、今は「お得感」や「実用性」に重きが置かれているものも多いです。
「福」の意味や価値も時代や世相を反映して変わってきたのでしょう。
しかし、「今年こそ!」と新年に誓いを立てたり、新しいことを始めたりするのは人の習いとして今も昔も変わりません。
時間の区切り方は色々でも、希望や期待を思わせる「新年」は事始めにもっともふさわしい区切りではないでしょうか。
大正から昭和にかけて活躍した作家の吉屋信子さんは、新年の思いを暦に託して「初暦 知らぬ月日の 美しく」と詠みました。
まっさらなノート、まっさらなシャツ、色々な「まっさら」がありますが、まだめくられていない初暦ほど「まっさら」という言葉が似合うものはないでしょう。
まっさらな暦には、まっさらな日々が眠っています。
まっさらな日々には、まっさらな時間が詰まっています。
今日から先は未知の世界であり、そこには個々の未来が静かに横たわっているのです。
商売をしていればままならないことの連続ですが、暦を一枚めくればその日は「過去」になり、その下には希望や期待で輝きながら目覚めのときを待つ「まっさらな未来」がほほ笑んでいるのです。
商売は長丁場。
行き当たりばったりで続けていけるものではありません。
経営には長期的な展望や戦略が必要だとされますし、実際にその通りでしょう。
しかしながらこれだけ時代のサイクルが速くなると、どれだけ長期的な目標を明確にしても10年後の社会情勢や環境がどうなっているかは誰も知る由はありません。
今のような時代には、少し先を見ながら「今年こそ!」を「今日こそ!」に替えて、暦を一枚ずつめくっていく感覚が似合っているように思えてなりません。
初暦は未知の宝庫のようなものです。
商売の成功や人生の充実というものは、「今日こそ!」の積み重ねの先にあるのかもしれませんね。
投稿者: