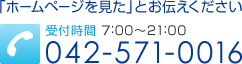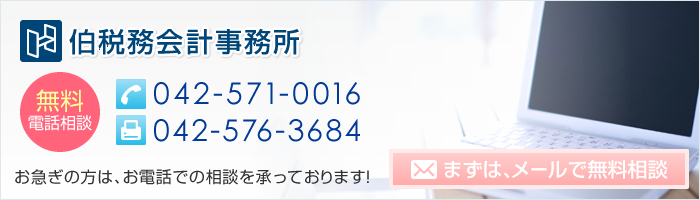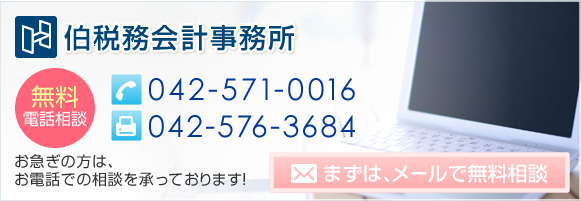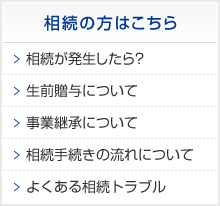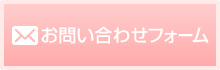2015.04.15更新
日本には「道」という考え方があります。「空手の道を極める」といえば、空手(武道)の精神真髄を学んで習得し、明らかにすること。その過程は「形から入り心に至る」です。
武道では、技の習得とともに礼節の大切さも合わせて指導しています。礼とは相手を尊敬し、自分を謙遜し、行いを丁寧にすること。節とはその場に応じた行動をわきまえることです。
しかし、こうした精神論だけを説かれてもなかなか理解できません。
そこで、稽古の前後に正座で黙想し、道場訓を斉唱してお互いにあいさつを交わすという「形」を繰り返す中で礼節の意味と大切さを理解して、それが身につき、やがて「心」に至るのだそうです。
誰にでも気持ちよくあいさつができ、自然と感謝の言葉が出て、敬う立場の相手には敬意をもって謙虚な態度で接する。
昔の日本人なら普通にやっていたことでしょう。それが今では、あいさつができるだけで「ちゃんとしている」とほめられるような時代です。
「感謝だ」「思いやりだ」「おもてなしだ」と声高に訴えても、形が崩れていたのでは心には至れないのではないでしょうか。
心という目に見えないものを整えるには、心としっかりつながっている「形としての所作(しょさ)」を整えることが大切なのだそうです。
わきまえのある所作は誰の目にも美しく映るだけでなく、礼節を重んじる人や折り目正しい人は周囲から好感を持たれ、信頼され、たくさんの人に慕われるでしょう。
たとえ初対面でも、相手のことをよく知らなくても、私たちは所作という形から多くを感じ取ってその人を判断しています。
心を整えたければ所作を美しく。折り目正しい行動は心の折り目を正します。
色々なことを頭で理解していても、それらを当たり前のこととして実践している人は存外少ないのが世の常ですが、「まずは自分から」の気持ちで振る舞いに気を付けたいものです。
商売繁盛とは、そうした先にあるのかもしれません。
投稿者: 伯税務会計事務所
2015.03.15更新
桜より一足早い春告花の「木瓜(ぼけ)」は、昔から俳句の題材として親しまれてきました。文豪の夏目漱石も大の木瓜ファンだったと聞きます。
小説『草枕』では、「木瓜は面白い花である。枝は頑固で、かつて曲った事がない。そんなら真直かと云ふと、決して真直でもない。(中略)そこへ、紅だか白だか要領を得ぬ花が安閑と咲く。柔らかい葉さへちらちらつける。評して見ると木瓜は花のうちで愚かにして悟ったものであろう」と主人公に語らせています。
木瓜の花言葉には「先駆者」や「指導者」のほかに「平凡」があります。梅によく似た花姿を個性がないと見た人がいたのかもしれませんが、漱石はその様子を「拙(せつ)」と表現し、「木瓜咲くや 漱石拙(せつ)を 守るべく」とい
う句を詠みました。
「稚拙(ちせつ)」や「拙劣(せつれつ)」の言葉からも分かるとおり「拙」とは下手なこと、つたないことを意味しており、「拙を守る」とは漱石が生き方の基本として好んだ言葉だそうです。
不器用で世渡り下手を自覚していた漱石ですが、器用で如才ない生き方に憧れていたわけではありません。むしろその逆で闇雲に利を追求するくらいなら、要領は悪くてもあえて拙を曲げない愚直な生き方を貫きたいという思いを込めて先の一句を詠んだのでしょう。
何かと巧みさが注目を集める世の中ですが、下手で不器用だから成功しないと考えるのはいかがなものでしょうか。自らの不器用さを自覚している人は不器用を克服するために懸命に努力します。片や、もともと器用な人はさほど苦労しなくても上手くいくため、得てしてあくせくしないものです。
努力なくして成長もないとするならば、成功の決め手は「器用」「不器用」ではないように感じます。むしろ器用であるゆえに努力を忘れ、そこで成長が止まってしまう恐れもあります。
足りないところを補う努力を忘れずに、不器用ながらも高い志を持ち、拙を守って自分らしく商売を続けていけたらどんなに素晴らしいことでしょう。
投稿者: 伯税務会計事務所
2015.02.15更新
あの訃報から約3ヶ月が経ちます。日本人の美学を集約したような稀代の名優、高倉健さんは、最期までご自身のスタイルを貫き通して旅立たれました。
高倉さんは読書家で、特に山本周五郎の描く男たちの世界に強く共感されていたことは有名です。中でも『晩秋』という短編がお好きだったと聞きました。
藩の立て直しを図るために情け容赦ない政治を執った進藤主計(かずえ)は、君主が代替わりすると過去の悪政の裁きを受ける身となりました。審判が下るまでの間、主計の身の回りの世話をすることになった都留(つる)は、かつて主計が切腹を命じた家中の娘でした。
亡き父の遺志を果たすため懐剣を胸に主計の世話を続けていた都留はある日、主計と客人の会話を盗み聞きし、主計の真意を知ることになります。最初から覚悟の上で悪役となり、世間からどんなに恨まれようと藩政改革のためにたゆまず屈せず闘ってきたこと。
目的が叶った今、「進藤主計」を悪政の首謀者として裁くシナリオを描いているのは、ほかならぬ主計自身であること。切腹を命じたある家中に対して今でも堪えがたい無念の気持ちを抱いていること――。
物語の最後、主計は「自然の移り変わりの中でも、晩秋という季節のしずかな美しさはかくべつだな」と晩秋を称えます。都留はそれを聞きながら、すべてを自分の胸の内に秘めて人生の幕を引こうとする主計の人生に思いを馳せるのでした。
「想いの強さ」というものを考えたとき、言葉に出したり人に伝えたりすることが自分の活力になる場合があります。成功者の多くが「夢を語れ」と指南するのは、言葉のパワーが物事を動かすことを体験的に知っているからでしょう。
しかし、逆もまた真なりではないでしょうか。
つい自分を主張したくなるのが人間ですが、強い信念は胸に秘め、愚痴も言い訳もなしに課せられた使命を果たし、一切の責任を自分が負った進藤主計の気高さは、そのまま孤高の名優に重なります。改めて高倉健さんのご冥福をお祈り申し上げます。
投稿者: 伯税務会計事務所
2015.01.15更新
新年にあたり今年の目標を立てた方も多いでしょう。ぜひともその目標を達成するために、「一行三昧(いちぎょうざんまい)」の気持ちで取り組んでいきたいものですね。
「これ」と決めたら心をひとつにして邁進することを「一行三昧」といいます。そこで、一行三昧がどのようなことかを物語る興味深い逸話をご紹介しましょう。
古代中国・漢の李将軍は勇猛な武人で知られた人物であり、特に弓術では天下無敵と称えられていました。
ある日、猟に出かけた将軍は一匹の大きな虎に出会います。大虎は将軍から遠く離れた場所にうずくまっていました。将軍はすぐさま矢を構え力の限り弦を引き、虎に向かって放ちました。
矢は見事に獲物をとらえ虎の体に矢が立ちました。「これはしめた!」と将軍は勢い込んで虎のそばへ走り寄りますが、虎だと思っていたのは実は虎の形をした大きな岩だったのです。岩に矢が立つなど古今東西聞いたこともない。
将軍は得意になり、もう一度やって見せようとばかりに再び矢を射りますが、何度やっても二度と岩に矢が立つことはありませんでした。
最初に「虎だ」と思ったときは、虎を射止めようとする一念以外、ほかには何もなかった将軍は、まさに「一行三昧」だったのです。ところが、岩に矢が立ったと知った後では、「俺の弓術はさすがだろう。どうだ見ておれ」という雑念が邪魔をして、一行三昧になりきれなかったのです。
茶人の千利休は茶の湯の極意を、「火をおこし、湯を沸かし、茶を喫(きっ)するまでのことなり、他事ある可(べ)からず」と述べたそうです。
様々な作法や決まり事がある茶の湯の世界にあって、なおそのことにしばられず淡々と茶をたしなむ。まさに一行三昧の極みです。
言うは易く行うは難しではありますが、素直な心で日常生活に向き合うことも一行三昧だそうです。時に弱い心に負けてしまったとしても、何度でも奮起して前を向き専心していきましょう!
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.12.15更新
年の瀬には新年に向けて「新品」を揃えたくなるものです。
そんな心理を知ってか知らでか、この時期になると風水で金運がアップするという「黄色い財布」の広告をよく見かけます。
もちろん黄色い財布にかえただけでお金が貯まるわけはなく、大前提として「基本」というものがあります。
例えば風水では、「水まわりをきれいにして風通しをよくしましょう」などといわれますが、ふだんの環境を整えることで「良い気」を呼び込み、結果として金運がアップしたり運気が良くなったりすると考えるのが自然でしょう。
商売をやっている人の中には縁起や験(げん)を気にする人が少なくないようです。
昔から言い伝えられてきたことは、言わば先人の知恵のようなもの。特に年末年始のような大きな区切りのタイミングには、襟を正す意味も込めて縁起や験をかついでおくと何かご利益に授かれるような気もします。
しかしながら「黄色い財布」の効果と同じく、いちばん大事なのは「ふだんの心がけ」であることはいうまでもないでしょう。
人生の処世哲学書として三百年以上も読み継がれてきた『菜根譚(さいこんたん)』の前集16項「四つの戒め」に、「利益は人より先に飛びつくな。善行は人に遅れをとるな。報酬は限度を超えてむさぼるな。修養はできるかぎりの努力を怠るな。」とあります。
強調より協調を、競争より協奏を。日頃からそんな心持ちで仕事をしていれば、商売の神様も喜んで味方してくれるというものでしょう。
ところで、「金運アップの財布なんて子ども騙しを誰が買うのかと思っていたら、夫のお財布がいつの間にか黄色にかわっていた」と笑うのはある社長の奥様。
「財布より妻を大事にしたほうがいいことあるよ」と手厳しいご意見ですが、確かにどんな縁起をかついだところで、ふだんから自分を気遣ってくれる人をないがしろにするようでは商売がうまくいくとは思えません。
慌ただしい年末年始ですが、どうか「ふだん」を大事にお過ごしください。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.11.15更新
人は何のために働くのか――。
内閣府の調査でも民間のアンケートでも、半数以上の人たちが「働く目的はお金(収入)を得るため」と答えています。
実際、お金を稼がなければ生活できないので当然の答えではありますが、経営者にとって従業員の仕事に対する意欲やモチベーションは気になるところでしょう。
人は本当にお金のためだけに頑張れるのか。今から80年ほど前に行われたある実験にひとつのヒントがありそうです。有名な「ホーソン工場実験」です。
実験では継電器の組み立て作業を行う6人のチームを作り、「賃金」「休憩時間」「軽食(おやつ)」などいくつかの条件を変えながら作業効率がどう変化するのか観察していきました。
賃金を上げる、休憩時間を増やす、休憩時間におやつを出す、これらの条件下では実験が進むにつれてチームの作業効率はアップしていきました。
こうした中、今度はすべての条件を元に戻してみたのです。賃金の額も休憩時間も元通り。軽食サービスは廃止。さて、チームの作業効率はどう変化したでしょうか。
意外なことに、労働条件をすべてリセットしたにもかかわらず作業効率は上がり続けました。つまり作業効率が上がった直接の原因は、賃金に代表される物理的な「労働条件」ではなく「人間関係」である。
これが実験から導き出された仮説でした。労働条件の変化によってチーム全体の雰囲気がよくなり、そこにチームワークが生まれたことで生産性が向上したというわけです。
人は一般的に、自分に関心や期待を寄せてくれる相手の気持ちに応えようとする傾向があります。
「大変な仕事だけどこのチームでならやっていける」「このリーダーのもとでなら頑張れる」という個人的な感情が、働く意欲やモチベーションの多くを占めているとするなら、「社長のためにひと肌脱ぐか」という社長ファンになってもらうことが究極のチームワークでありリーダーシップなのかもしれません。
リーダーたるもの「魅力的な人」であり続けたいものですね。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.10.15更新
商売がうまくいっているケースを見ると、結局は社長の人柄がものをいうのだろうと考えさせられることが多々あります。
「100万分の1グラム」という世界最小の歯車を生み出して、一躍脚光を浴びた樹研工業の松 浦元男社長は、地元の暴走族などを社員として受け入れてきたことでも知られています。
創業以来、人の採用は先着順。学歴も国籍も性別も問わず、履歴書も見なければ面接も試験もなし。「誰もが無限の可能性を秘めた存在」が松浦社長のモットーで、その背景には「人は本来"善い生き物"」という前向きな姿勢で人を信用しようとする気持ちがあるようです。
成果主義や合理主義とは正反対の松浦流経営手法を、「そんな精神論は聞き飽きた」と思う方もいるかもしれません。松浦社長自身も最初は「こいつらで大丈夫か?」と疑心暗鬼だったそうです。
しかし、入社したばかりの社員には工場で徹底的に基本を叩き込み、世界に通用する技術者に育て上げる仕組みを整え、何年もかけて人材を育成した結果が「世界最小の歯車」につながりました。
前向きな姿勢で人を信じる気持ちがあれば社員は期待以上の成果を出す。この信念は、そのまま松浦社長の人柄に通じているといえるでしょう。リーダー(君子)の資質について多くの言葉を残している孔子は、『論語』の中で「君子に九思あり」と説いています。
孔子自身が立派なリーダーでありながらも、常にこの「九思」をもって自らを磨いていたのです。
1.物事の本質を明確に見ること
2.人の話はちゃんと聞くこと
3.穏やかな表情を保つこと
4.謙虚にふるまうこと
5.言行一致で誠実に話すこと
6.仕事は慎重かつ尊敬の念を持って行うこと
7.疑問があったら質問すること
8.怒るときはしこりが残らぬようにすること
9.うまい話にはのらぬこと
社長の人柄は多かれ少なかれ商売に影響を与えるようです。だとすれば、九思の実践は容易ではありませんが、自分を成長させる糧として、ひいては商売を成功させる策のひとつとして先人の教えを心に刻んでおきたいものです。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.09.15更新
ある社長が、ひょんなことからまったく異業種である親友のマッサージ店を手伝うことになったそうです。
成り行き上なんとなく始めたことですが、気がつけばマネージャーとして約10人の社員をとりまとめ、ゴチャゴチャだった経営方針を整理して、会社の方向性の舵取りをして、今では本業よりマネージャー業の方が忙しいくらいだとまんざらでもないようです。
社長は、まったく畑違いの分野にいきなり飛び込んで成果を上げた理由を、「専門家になろうとしなかったから」だと自己分析したそうです。社長にマッサージの専門知識があれば何かとスムーズだったかもしれません。実際、「何も知らない素人に言われたくない」という雰囲気を感じたこともあったそうです。
しかし、社長は積極的に勉強しようとはしませんでした。むしろ、社内改革には自分の素人目線が武器になると踏んでいたようです。
長らく同じ業界にいると、その業界の常識が世間の常識だと思い込んでしまいがちです。
無意識のうちに業界の固定観念が物事の判断基準になっているので、外からの意見に対しては「○○なはずだ」「○○するべきだ」と聞き入れようとしない。つまり、専門家になればなるほど視野が狭くなるという皮肉が起こり得るのです。
専門家とは「できない理由」を探す人かもしれない。
そう感じていた社長はあえてマッサージ業界から少し距離を置き、素人目線をなくさないようにしたと言います。そのため時には突拍子のない意見も出しますが、業界に染まっていないからこそのお客様目線のアイデアはその何倍もあるそうです。
専門家として高度な知識や技術を役立てるのは素晴らしいことですが、残念ながら「井の中の蛙」になってしまった専門家も少なくありません。
専門家になっても「できない理由」を探し始めることにならないよう、お客様目線を忘れずにまずはやってみようとする「素人のチャレンジ精神」を大事にしながら商売をしていきたいものですね。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.08.15更新
経済は感情で動くといわれます。また、世界情勢も感情で動くといわれます。なぜなら人が感情で動くからです。
商売にもやはり感情が入り込みます。例えば同じ失敗をしても許される人と責められる人がいるのは、受け取る側の「好き嫌い」や「たまたまの気分」によるところも大きいでしょう。
取引相手の気分によって商売に不利益がもたらされるのは残念な話ですが、あなたの感情も商売相手に影響を及ぼしているかもしれません。仕事に私情は禁物だという意見はごもっともです。しかし、実際は商売の様々な場面で多少なりとも感情が影響を及ぼし、しかもその割合は決して小さくないようです。
たとえ無意識でも感情に左右されるのはお互い様。それを理解した上で商売のやり方を見直すと、自分だけで決着する事柄は思いのほか少ないことに気付くでしょう。つまり商売では、相手にゆだねなくてはならない部分がけっこう多いということです。
経営者の中には、何から何まで自分でコントロールしないと気が済まないタイプの人がいますが、相手にゆだねる部分がある以上、すべてをコントロールするのはなかなか難しいものです。なぜなら人の感情をコントロールするのは、売上げを伸ばすこととはまた別の能力だからです。
また、すべてに全力投球する姿勢は素晴らしいことだと思いますが、自分の「感情」というボールを常に相手に全力投球することが必ずしもよい仕事につながるとは限らないでしょう。
相手の真意を探るためにおどけたふりをしたり、相手に花を持たせるためにあえて7割のところでやめたりといったことが必要な場面も多々あります。相手の感情をコントロールするより、感情の影響力を最小限にとどめる工夫をする。
常に最強で行こうとするより、「今」に最善を尽くす。それがよい仕事につながっていくのではないでしょうか。目の前の仕事や出来事に意識を向けて、今の状況に最も適した判断と行動をすることで、移ろいやすい感情に振り回されることなく、自分自身のブレない軸をしっかり持ち続けていきましょう。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.07.15更新
若者のクルマ離れが進んで若者相手の販売台数が伸び悩んでいる今、メーカーはクルマの「使い道」を提案するCM作りに余念がありません。
カッコイイ走りを見せるのがかつてのCMなら、今は親子で海に行くシチュエーションを設定したり、荷物の多いママに「こんなに収納があって便利ですよ」と呼びかけたり、クルマの使い道を懸命にアピールしています。
販売店でもクルマの使い道を具体的に提案しながら、「このクルマがあると○○できて便利ですよ」「このクルマに乗って○○に行きましょう」などとお客様にイメージさせるのだそうです。
欲しいものを積極的に求める能動型の消費が影を潜めるなか、消費者の興味を引くために企業は様々な工夫をします。使い道の提案はそのひとつでしょう。
何かを連想させることで消費者の背中を押し、消費行動を刺激しようというわけです。
オンライン書店のアマゾンなどは顧客の購入履歴や閲覧履歴から、同じ著者の別の作品や関連性の高い商品などを「おすすめ商品」としてページ内で推薦しています。
これは「レコメンデーション(推薦)機能」と呼ばれ、顧客の検索履歴や購入履歴から次の購入を促そうというサービスです。時と場合によっては煩わしくも感じられますが、何となく気になってお勧め商品をクリックして、「これはいいかも!」とそのまま購入してしまうことは確かにあります。
自分の視点だけでは探し出せなかったものに出会い、意識していなかった自分の欲求に気付く。
レコメンデーション機能は、連想によって気付きを与え、行動させるための新しい消費ツールといったところでしょうか。
物と情報に溢れた現代は「選びきれない」時代ともいえます。商売でも「連想させて背中を押す」方法で、顧客の選択肢に分け入っていく工夫が必要なのかもしれません。
けれどそれはマーケティングうんぬんではなく、突き詰めれば「お客様に喜んでもらえるようどれだけ知恵を絞っているか」ではないでしょうか。
投稿者: 伯税務会計事務所