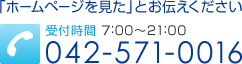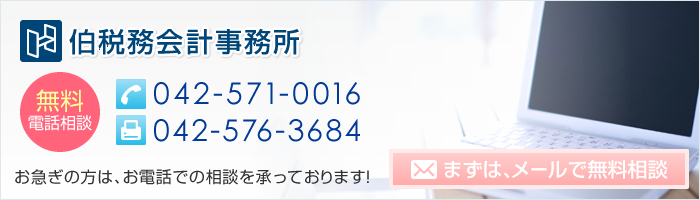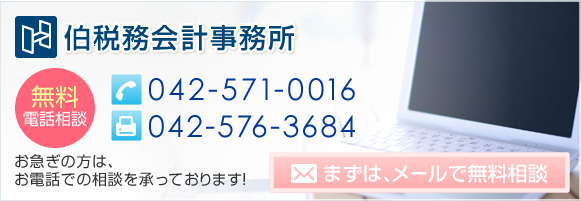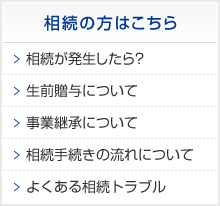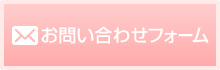2014.08.15更新
経済は感情で動くといわれます。また、世界情勢も感情で動くといわれます。なぜなら人が感情で動くからです。
商売にもやはり感情が入り込みます。例えば同じ失敗をしても許される人と責められる人がいるのは、受け取る側の「好き嫌い」や「たまたまの気分」によるところも大きいでしょう。
取引相手の気分によって商売に不利益がもたらされるのは残念な話ですが、あなたの感情も商売相手に影響を及ぼしているかもしれません。仕事に私情は禁物だという意見はごもっともです。しかし、実際は商売の様々な場面で多少なりとも感情が影響を及ぼし、しかもその割合は決して小さくないようです。
たとえ無意識でも感情に左右されるのはお互い様。それを理解した上で商売のやり方を見直すと、自分だけで決着する事柄は思いのほか少ないことに気付くでしょう。つまり商売では、相手にゆだねなくてはならない部分がけっこう多いということです。
経営者の中には、何から何まで自分でコントロールしないと気が済まないタイプの人がいますが、相手にゆだねる部分がある以上、すべてをコントロールするのはなかなか難しいものです。なぜなら人の感情をコントロールするのは、売上げを伸ばすこととはまた別の能力だからです。
また、すべてに全力投球する姿勢は素晴らしいことだと思いますが、自分の「感情」というボールを常に相手に全力投球することが必ずしもよい仕事につながるとは限らないでしょう。
相手の真意を探るためにおどけたふりをしたり、相手に花を持たせるためにあえて7割のところでやめたりといったことが必要な場面も多々あります。相手の感情をコントロールするより、感情の影響力を最小限にとどめる工夫をする。
常に最強で行こうとするより、「今」に最善を尽くす。それがよい仕事につながっていくのではないでしょうか。目の前の仕事や出来事に意識を向けて、今の状況に最も適した判断と行動をすることで、移ろいやすい感情に振り回されることなく、自分自身のブレない軸をしっかり持ち続けていきましょう。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.07.15更新
若者のクルマ離れが進んで若者相手の販売台数が伸び悩んでいる今、メーカーはクルマの「使い道」を提案するCM作りに余念がありません。
カッコイイ走りを見せるのがかつてのCMなら、今は親子で海に行くシチュエーションを設定したり、荷物の多いママに「こんなに収納があって便利ですよ」と呼びかけたり、クルマの使い道を懸命にアピールしています。
販売店でもクルマの使い道を具体的に提案しながら、「このクルマがあると○○できて便利ですよ」「このクルマに乗って○○に行きましょう」などとお客様にイメージさせるのだそうです。
欲しいものを積極的に求める能動型の消費が影を潜めるなか、消費者の興味を引くために企業は様々な工夫をします。使い道の提案はそのひとつでしょう。
何かを連想させることで消費者の背中を押し、消費行動を刺激しようというわけです。
オンライン書店のアマゾンなどは顧客の購入履歴や閲覧履歴から、同じ著者の別の作品や関連性の高い商品などを「おすすめ商品」としてページ内で推薦しています。
これは「レコメンデーション(推薦)機能」と呼ばれ、顧客の検索履歴や購入履歴から次の購入を促そうというサービスです。時と場合によっては煩わしくも感じられますが、何となく気になってお勧め商品をクリックして、「これはいいかも!」とそのまま購入してしまうことは確かにあります。
自分の視点だけでは探し出せなかったものに出会い、意識していなかった自分の欲求に気付く。
レコメンデーション機能は、連想によって気付きを与え、行動させるための新しい消費ツールといったところでしょうか。
物と情報に溢れた現代は「選びきれない」時代ともいえます。商売でも「連想させて背中を押す」方法で、顧客の選択肢に分け入っていく工夫が必要なのかもしれません。
けれどそれはマーケティングうんぬんではなく、突き詰めれば「お客様に喜んでもらえるようどれだけ知恵を絞っているか」ではないでしょうか。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.06.15更新
今では当たり前のように使われている「有言実行」という四字熟語。ご存知のように「言ったことは必ず実行する」という意味で、責任を問う場面などでよく耳にします。
しかし、「有言実行」はもともとの言葉ではなく、「不言実行」から派生した造語のようなものだそうです。不言実行とは、文句や理屈を言わずに黙って「なすべきことをする」こと。
かつて、奥ゆかしさや慎ましさをよしとした時代には、不言実行が美徳とされました。
「古者の、言をこれ出ださざるは、躬(み)の逮(およ)ばざるを恥づればなり」とは孔子の『論語』の一節で、昔の賢者が軽々しく言葉を口にしなかったのは、自分の言葉に実行が追いつかないのを恥としたためであるといった意味でしょうか。
つまり、自分で言ったことを実行できないのは恥だと考えていた孔子は、言葉には慎重であるようにと説いたのです。
軽はずみな言動は恥どころか信用を失います。孔子の言うとおり言葉には慎重でありたいものですが、最近は有言実行の意味合いが「やろうとしていることを口に出す」に変わってきて、不言実行より立派な態度だと見なされる傾向があります。
そのせいか、自分の思いや目標を口にしてアピールすることが、成功の秘訣だという風潮も感じられます。
口ばかりの「有言不実行」に比べたら、約束事を口にして自ら退路を断ち、覚悟をもって行動することは大したものです。
しかし、努力を人に言わず、その姿を見せもせず、人知れず淡々とひたむきに成果を出し、けれど自慢することもなく、それでもなお努力を続けることは、純粋に自分との勝負である分、口に出す以上に強い信念が問われるものです。
気軽に言葉にしないで胸の内に秘めた思いが本物であれば、やがて成熟して実りの時を迎えるでしょう。
そのときあなたの言葉にはさらに重みが増し、振り返ればそこには確かな足跡が刻まれていることだと思います。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.05.15更新
ある会社のA社長は組織というものを「クルマ」に例えていました。
「クルマはエンジンやハンドルやタイヤなど様々な部品の集合体だが、部品だけを集めてもクルマにならない。
各部品がコードでつながってはじめてクルマという完成品ができあがり、ようやく動くようになる。
これは組織も同じだろう」と。
組織には上下関係がありますが、上下の関係だけで成り立っているうちは単なる人の集合体で自主性も協調性も創造性も期待できません。
しかし、上下関係の中にも横のつながりが生まれるとチームとして機能しはじめます。横のつながりとはクルマでいう部品同士をつなげる「コード」のようなもの、すなわち人間関係なのです。
ところが、人間関係にはクルマをつくるような「決められた工程」がありません。相手にも感情があるので、「今から人間関係を結ぼうじゃないか!」「そうしよう!」とはいかないから苦労するのだとA社長は言います。
そこでA社長が心掛けていることは、部下から「この人は信頼できそうだ」と思ってもらえる行動だそうです。基本は小さな約束を守ること。つまり言動の一致です。
「明日の朝電話する」と言ったら翌日の朝一番で電話を入れる。それが小さな用事でも、朝一番で電話する必要性がなくても、約束を守ってもらえると「私はこの人から大事にされている」と感じて、自然と相手に好意を持つものだとか。
心理学的には「信頼」と「好意」は同一次元のポジティブな感情とされており、相手から好意を持ってもらえると信頼関係を築きやすいのだそうです。
「すぐに確認してきます」と言って悠長に歩いて行く人と、その場から急ぎ足で立ち去る人と、どちらが好印象かは比べるまでもありません。
言葉と行動の一致は好意につながります。
好意は「見えないコード」となって人と人を結び、やがて「信頼」というクルマが動き出します。
上下関係だけでも仕事はできますが、そこに人間同士の付き合いがあれば血の通った組織となるのでしょう。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.04.15更新
目標の達成や夢の実現にはプラス思考が大切だと言われます。
成功するためには「成功したイメージを思い描きましょう」とも言われます。物事をポジティブに捉え、明るい未来をイメージするのはよいことだと思いますが、そのプラス思考が成功の足かせになっていたら・・・。ある実験をご紹介しましょう。
心理学者のリチャード・ワイズマン博士は、やる気を高める心理について大規模な調査を行いました。対象者は目標や夢の実現を目指す世界中の人たち5000人以上。
就職、ダイエット、結婚、禁煙など各々が目標を掲げ、調査を開始した当初は大半の人が自分の成功を確信していたようです。
ところが最終的に目標を達成した人はわずか10%でした。
目標達成に向けて「効果があった」と報告された方法で多かったのは、「段階的に着実な計画を立てる」「目標を人に話す」「成功した場合に起こる相乗効果を考える」「小さな目標を達成したら自分にご褒美を与える」「目標達成までの進捗を記録する」でしたが、興味深いのは「効果がなかった」とされた5つの行動です。
1.成功した人物を思い浮かべてやる気を起こす
2.失敗した場合に起きる嫌なことを考える
3.目標達成を邪魔するマイナス要因を頭からしめ出す
4.意志の力に頼る
5.成功者になった素晴らしい自分を思い描く
つまり、プラス思考だけでは物事は改善しないし、成功した自分を思い描いても成功しない。
それどころか逆効果だというわけです。
自分にハッパをかけ、成功者を思い浮かべ、成功した自分の姿をイメージしてきた経営者にはショッキングな調査結果でしょう。
イメージトレーニングの効果はスポーツ選手などが証明していますが、今のイメトレは「成功した自分を思い描く」より「失敗したときにどう対処するか」により重きを置いているようです。
理想は高く、けれど「失敗した場合に起きる嫌なこと」を直視して、さらに次の克服法を具体的に考える。
これがワイズマン博士からの目標達成に向けたアドバイスです。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.03.15更新
誰に出逢うかで人生は大きく変わると言われますが、果たしてそうでしょうか。
曹洞宗の開祖である道元禅師が中国に渡り念願の師に出逢ったとき、その喜びを「まのあたり先師(せんし)をみる。これ人にあふなり」という感動の言葉で表しました。
求め続けた師に逢うためにはるばる海を越え、ついに願いが叶ったとき道元禅師は思ったのです。
自分一人で考えて行動したのでは分からないことがある。人との出逢い、それがすべての始まりであると。
これを禅語で「我逢人(がほうじん)」と言います。
「我、人と逢うなり」という意味ですが、「誰」と出逢うかではなく、出逢いそのものの尊さを三文字で表したものです。
人はみんな違った考え方を持ち、それぞれの人生を生きています。
自分と似ている人はいても同じ人は一人もいません。
ですから人は出逢いによって自分とは違う価値観に気付いたり、自分の中で答え合わせをしたりして少しずつ成長していけるのでしょう。
人との出逢いは未知なる自分との出逢いでもあります。
人に出逢わなければ自分の世界はいつまでも広がらず、深みも増すことなく目の前の景色は変わっていきません。
人がうらやむような出逢いでも、傍からはちっぽけに見える出逢いでも、「人が人に出逢う」ことにおいてはすべて同じ「出逢い」でしょう。
確かに「誰」に出逢うかで人生は変わりますが、そもそも人と人との「出逢い」そのものがありがたいとなれば、良い出逢い・悪い出逢いの区別はありません。
そのときは後味の悪い出逢いだったとしても、あとから振り返ったときに「あの出逢いがあったからこそ今の自分があ
る」と省みることができたなら、それこそ成長の証でしょう。
商売はご縁のたまものです。人との出逢いを大切にして、「良い・悪い」で判断せずに出逢いそのものを楽しみたいものです。
出逢いを大切にしていれば出逢いが出逢いを呼びます。つまりそれは人を大切にすることだろうと思います。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.02.15更新
時間に対する考え方や習慣と年収の関係を調べた調査結果があります。
年収400万円台の人たちと1500万円以上の人たちに、「人生の目的や目標を常に意識している」「仕事の目的や意味を常に考えている」「やりたいことリストを作っている」「グチを言わない」「迷ったら新しい選択肢を選ぶ」などの質問をしたところ、どの設問に対しても「当てはまる」と答えた率が高かったのは年収1500万円以上の人たちでした。
目的意識を高く持って常にチャレンジし、失敗してもクヨクヨしないで先に進む。つまり年収の差を生む要因のひとつは「時間」に対する考え方で、「時間」の意識が高い人ほど成功の確率が上がるのかもしれません。
「お金と時間はどちらが大切か」というのは古くて新しい問いです。
際限なく増やしたり貯めたりできて、しかも貸し借りまでできるお金に対して、増やすことも貯めることも貸し借りもできず、一度失うと二度と取り戻せない時間のほうがはるかに大切な資源だというのは、商売をしている人なら常々感じていることでしょう。
しかし、「たいていの経営者は、その時間の大半を"きのう"の諸問題に費やしている」(ピーター・ドラッカー)。これが現実かもしれません。
西洋のことわざは「時は"金"なり(Time is money)」ですが、商売上手で知られる華僑の人たちは「時は"命"なり」と言うそうです。これは相手の時間に対しても同じことが言えるでしょう。
例えば商談のために1時間作ってもらうのであれば、商談相手の命の中の1時間分を分けてもらっていると考えるのです。商談に15分遅れたら相手の命を15分間ムダにしたことになります。
何の準備もなしに適当な商談をしたら、相手の命はもちろん自分の命も1時間分のムダ遣いです。改めて時間の重要性に意識を向けてみたいですね。
濃密で意義のある時間を過ごせるかどうかは、商売の成功と共に豊かな人生のためのテーマでしょう。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.01.15更新
今年の干支である「午」を動物に当てはめると「馬」になります。
馬にちなんだ故事ことわざはいくつもありますが、座右の銘にあげる人が多い故事成語といえば「人間万事塞翁が馬」でしょう。
幸せと不幸せは予測のしようがないというたとえで、だから目の前のことに一喜一憂しても仕方ないというわけです。せっかくなので語源をご紹介します。
ある老人が大事にしていた馬が逃げてしまい、気の毒に思った近所の人が老人をなぐさめると「これが不幸とは限らない」と平然としています。しばらくして逃げ出した馬が立派な馬を連れて帰ってきたので近所の人がお祝いに行くと、今度は「これが幸福とは限らない」と老人は言います。
息子がその馬で落馬して骨折したときも、老人はお見舞いに来てくれた近所の人にまたしても「これが不幸とは限らない」と言うのです。
1年後、大きな戦争が起こりました。大勢の若者が犠牲になった中、老人の息子は無事でした。落馬による骨折で足を悪くしたので兵役を免れたのです。ただ、これが幸福とも限りません。
こんな実話もあります。小さい頃から「点描」(小さな点で作品を描く画法)で絵を描いていたフィル・ハンセン少年は、点描のやりすぎで手が震える病気になり、思うような「点」が描けなくなってしまいました。
そのため泣く泣くサラリーマンになりました。しかし、どうしても芸術家になる夢をあきらめきれなかったフィルはある日、手の震えに任せた「点」のようなもので見事な作品を描き上げました。
X線技師として働きながら、今ではマルチメディアアーティストとしても活躍しているフィルは言います。「制約があるほうが創造力を発揮できる」と。
ところで、馬の瞳孔は横長で、顔の左右に目がついているので視野は350度にも及びます。
真後ろ以外を見渡せる馬のようにはいかないとしても、できるだけ広い視野を持って商売にのぞみたいものですね。人生、何が幸いするかわかりません。
目の前の小さなことに一喜一憂せず今年も邁進していきましょう!
投稿者: 伯税務会計事務所
2013.12.15更新
65歳の誕生日に社長の座を息子に譲ったある男性のお話です。
長年、小売業を営んできた彼は、「経営者からふつうのオジサンになって最初にやったのは、養護学校の文化祭を手伝うボランティアでした」と話していました。
社長退任の時期も、ボランティア活動も60歳から決めていたそうです。養護学校の文化祭の当日、担当するクラスの生徒たちにあいさつをしました。
「名刺なしの自己紹介なんて学生時代以来だなぁ」と感慨深かったそうです。
クラスの出し物はポップコーンの販売で、彼は14歳のK君と一緒に会計係を頼まれました。ところが、「主役は子どもたち。
自分はフォローする立場」と自分に言い聞かせてK君を手伝っていたつもりが、気が付けばお金をもらって食券を渡す一連の作業をすべて彼がやっていたそうです。
小売業者としてお客様をお待たせしない商売を心掛けてきた彼は、今までの癖で「K君がもたもたしているとお客様を待たせてしまう」と思ってしまったのです。
しかし、確かにK君は言葉も手の動きもおぼつかず、食券と一緒に100円玉を渡してしまう状態だったそうですが文句を言う人は一人もいません。
お待たせしたらお客様がイライラすると気にしているのは自分だけで、目の前のお客様たちはK君が一生懸命にやっている姿をニコニコしながら待っている。
こんなときでも合理的に効率を重視してしまう自分に、冷や汗が出る思いだったと彼は振り返っていました。ふつうのオジサンになった彼は改めて考えたそうです。
文化祭では小売業のプロである自分より、K君のほうがよほどお客様との距離が近かった。長年、お客様のために頑張ってきたつもりだが、「お客様のため」とは一体何だろう。
自分は本当にお客様のほうを向いた商売をしてきたのだろうか。経営者からふつうのオジサンになってはじめてそう感じたそうです。
「経営者のときはお客様のためにと脇目も振らずに突き進んだけれど、前ばかり見ていると大切なものを見落としてしまいますね。
たまには右や左、上や下も見ないといけないですね」と彼は言っていました。
投稿者: 伯税務会計事務所
2013.11.15更新
「平常心是道(びょうじょうしんぜどう)」は禅語の中でもっとも有名な一語でしょう。曹洞宗の瑩山(けいざん)禅師は、平常心を次のように言い表したそうです。
「茶に逢うては茶を喫し、飯に逢うては飯を喫す(さにおうてはさをきっし、はんにおうてははんをきっす)」。お茶が出てくればお茶を飲み、ご飯のときにはご飯を食べる、ただそれだけのこと。つまりそこに雑念はないというわけです。
日常の当たり前の行ないを積み重ねる。余計なことを考えず、当たり前のことを丁寧に行なって大切に育んでいく日々が「平常心」というもののようです。小さいことにクヨクヨせず、細かいことにこだわることなく、毎日を伸び伸び生きて人生を味わい尽くせたらどんなに素晴らしいでしょう。
しかし、人は泣いたり笑ったり、悩んだり苦しんだりしながら生きていくもので、心が揺れ動くのは当たり前です。商売をしていればなおさらのこと、「ふだん通りにしよう」「緊張してはだめだ」と平常心を意識した途端に平常心を離れてしまうという皮肉が起こるものです。
人の心を動揺させる8つの要素を禅の言葉で「八風」と言います。
8つの要素とは「利、衰、毀(き)、誉、称、譏(ぎ)、苦、楽」。利(うるおい)は成功すること。衰(おとろえ)は失敗すること。毀(やぶれ)は陰で誹(そし)ること。誉(ほまれ)は陰でほめること。称(たたえ)は面と向かってほめること。譏(そしり)は面と向かって誹ること。苦(くるしみ)は苦しいこと。楽(たのしみ)は楽しいこと。
人生の波風はほとんどが「八風」のどれかであり、「八風」に動じることなく天辺の月のような不動心を持って生きるようにと戒(いさ)めた禅語が「八風吹けども動ぜず天辺の月」です。
今年も残り少なくなり日ごとに慌ただしさが増していきますが、あれもこれもと考えすぎれば八風に足をすくわれます。今できることに心を尽くして、「当たり前」を大事にしていきましょう。商売にも人生にも近道はありません。
投稿者: 伯税務会計事務所